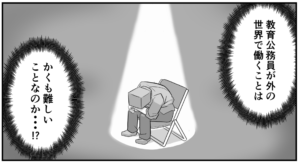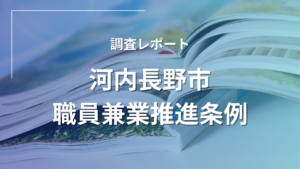各種メディアやSNSで多くの情報が氾濫する現代において、多様な働き方を実践し自分らしく生きる人の姿を目にする機会が増えてきました。
そんな折、学校の中ではICT化が前進してはいるものの、「まだまだ文化的・慣習的側面でアップデートしきれていないのではないか」と感じる人も多いのではないでしょうか。
子どもたちの前に立ち、また並走する立場である教師として、
現代社会に目を向け、自分自身でも学校の外の世界を体感したいと感じることは、本来教師としてあるべき姿であるという味方もできます。
本記事では、学校の外の世界を体感する方法は数ある中、教員の副業・兼業について実情をご紹介し、さらには「複業」の考え方もお伝えしていきます。

前田 央昭
特定非営利活動法人越境先生 代表理事
/Edtech企業社員/著述家/個人事業主
学校の先生の越境を起点に社会開発をすべく活動中。
著書「先生が複業について知りたくなったら読む本」学事出版
経歴:現在←小学校非常勤×個人事業主←中学校理科教諭←大阪教育大学←吉本新喜劇←工業高校
「やってみたい。でも本当にやっていいの?」
この記事を読んでくださっている方なら一度は抱いたことのある感情ではないでしょうか。
今の働き方にどこか息苦しさを感じている。でも、周囲はみんな黙々と働いている。(ように見える)
そんな中で、「副業してみたい」と思うこと自体が悪いことのような気がして、心の中にそっとしまい込む。
私もそうでした。
中学校の教員としてフルタイムで働いていた頃、
教室の外の世界に出たいという思いが心の奥底でくすぶり続けていました。
でも、副業なんてやってる先生なんて周りにほとんどいなかった。
仮にいたとしても、それを堂々と言える空気ではなかったように思います。
「やっていいのか?」という制度的な疑問もさることながら、
「そんな考えを持ていいのか?」という感情的な不安が先に立っていました。
結論:教員の副業は制度上、可能です
まず事実として、公立の教員であっても、副業は制度上、可能です。
地方公務員法第38条や教育公務員特例法第17条において、
営利企業への従事は原則制限されていますが、例外として「許可を得れば兼業を行うことができる」とされています。
「原則禁止・許可制」という制度の枠組み。
これは教員だけに限った話ではなく、多くの地方公務員に共通するものです。
実際に許可を得て兼業に従事している先生はいますが、ここで問題になるのが——
「許可は取れるけど、取るまでがめちゃくちゃ面倒くさい」という現場のリアルです。
「バレずにやる方法はあるのか」という発想を断ずる勇気を持つ
大前提みなさんに強くお伝えしたいのは、
「バレずにやる方法はあるのか」という発想を断ずる勇気を持っていただきたいということです。
教師なんだからそんなことは当然だろう、と言われればその通りですが、
そうは言っても副業を体験してみたいという好奇心によって良くない考えが頭をよぎってしまうこともあるかもしれません。
この考えは違法行為であるということからもあってはならないのですが、中長期の合理性の観点で見てもあまり賢いやり方とは言えません。
違法な副業をしたという負目は一生ついて回りますし、せっかく積んだ実績も一生公開することができません。
また、教師であるアイデンティティを傷つけることにもなりますので、目先の「バレずにやろう」という負の囁きを断ずるようにしてください。
本記事を掲載している越境先生の活動が身を結び、教員が副業しやすくなる社会をぜひ準備してお待ちいただきたい。

副業を考えた時、最初の壁は“制度”ではなく“空気”
さて、話を現在の副業に戻しましょう。
私が越境先生として、副業に挑戦する教員の相談を受けてきた中で痛感したのは、
制度の壁と、文化・慣習の壁があるということ。
「申請したら、校長先生にどう思われるかが不安」
「こんなに忙しいのに外で活動だなんて、と思われるのも、、、」
「申請の手続きが煩雑な上に、結局は不許可になってしまった。」
そんな声を、本当にたくさん聞いてきました。
実際に、管理職の先生の理解度や実際にその自治体で運用されている制度の厳格さにはばらつきがります。
いわゆる”ガチャ”のような状況に翻弄される方も残念ながら何件も目にしてきました。
制度的にはできるはずだけど、「やりたい」と言える雰囲気ではないし申請しても通りにくい——
こういった状況が全国的に起こっているというのが教員の副業の現状です。
それでも、副業に関心を持つ先生が増えている理由
では、なぜそんなにやりにくい環境の中で、
それでも副業に挑戦する教員が増えてきているのでしょうか?
お金のためだけではなさそう
私が過去にとったアンケートや社会の動向から見えてきたのは
「お金のため」だけではない、別の理由も大いに関わっていると考えています。
たとえば——
- 教室の外に広がる世界を体感してみたい
- 自分の価値が社会にどう還元できるのか試してみたい
- 学校の外で得た学びを子どもたちに還していきたい
そんな願いを胸に、一歩踏み出そうと考える先生が増えてきているように思います。
私自身もそうでした。
釣り系YouTubeチャンネルを立ち上げ、
SEOサイトを自分で構築し、
教育以外の世界に飛び込む中で、
「教師という仕事」が改めてどんなに尊いかを知ると同時に、外の世界で得たこの感覚を学校に還したいと強く願うようになりました。
多様な働き方が可視化されるようになってきた
学校の外に目を向けてみると、民間企業でも多様な働き方が認められるような動きが見られるようになってきました。
以下はその一例です。
| 企業 | 副業・越境の特徴 | ポイント |
|---|---|---|
| パナソニックグループ | 2023年度に258 名が「社外副業」を実施。公式DEIサイトで“社外副業”を正面から紹介。 | 老舗製造業でも「外で学び、社内へ還元」がウェルビーイング策と定義。 |
| 富士通 | 採用ページで「副業をはじめとする社外での活動を応援」と明記。 | “キャリアオーナーシップ”を掲げ、社員の自律的な学びを推進。 |
| 日立ソリューションズ | 2025/3 に社内副業マッチングサービスを社内向けに実装。時間単位で他部門の仕事に挑戦できる仕組みを外販も開始。 | 社内リソースをシェアしながらスキル開発とモチベーション向上を両立。 |
| ANAグループ | 2024 年度から「社内兼業インターンシップ」を展開。客室乗務員が広報や新規事業へ越境する事例を公開。 | 本業シフトの難しい航空業界でも、兼業を人材育成策と位置づけ。 |
学校の外に関心の向く先生であれば、世の中のこのような状況を敏感に察知していると考えられます。
私の元に相談に来るみなさんの意見としても、「子どもの伴走者として、まず自分が広い世界に触れてみたいと考えている」という姿勢を持たれている先生が年々増えているように実感しています。
実際、どんな副業なら許可が出やすいの?
どんな副業なら許可がおりやすいか、これはよく聞かれる質問のひとつですが、
傾向としては以下のような分類ができます。
- 許可が出やすいもの
- 大学の非常勤講師
- 教育書の出版
- 教育手法のセミナー講師
- NPOなど非営利団体での活動
- 許可を得ずに実施できるもの
- 5棟10室未満の不動産経営
- 株式や投資信託など一般的な証券投資
- 一定規模以下の太陽光発電
- 単発の講演や寄稿に対する謝金など
※細く説明を後述
- 許可を得にくいもの
- 営利企業の役員等への就任
- 営利企業への継続的な従事
- 個人事業の立ち上げ
これらはあくまで傾向であって、最終的には「勤務先がどう判断するか」に委ねられる側面が強いのが実情です。
許可を得る方法や実際の事例は拙著「先生が複業について知りたくなったら読む本」(学事出版)をお読みいただけますと幸いです。
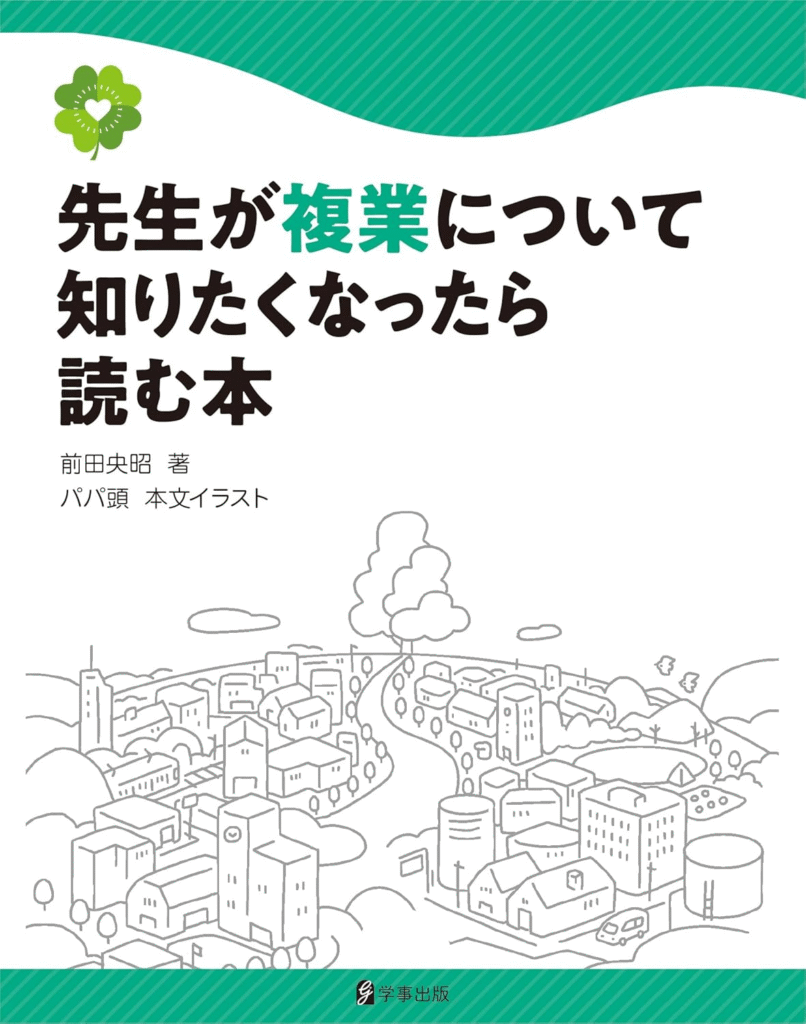
「副業」を越えて、「複業」へ
当サイトを運営する特定非営利活動法人越境先生は、もっと先生が越境しやすくなるよう、副業しやすい社会にしたいと考えています。一方で「副業解禁」だけをゴールにしていません。
むしろ私たちが大切にしているのは、“複業”という考え方です。
「副業」が“収入を増やすための第二の仕事”だとしたら、
「複業」は、自分の中に複数の側面があってもいいのではないか、という考え方です。
学校に留まり続けて教科指導の方法を深化させることももちろん尊い。
しかし不確実性が増す現代社会において、内なる多様性を持った教師がいてもいい。
むしろ一定数冒険心を持った先生が学校にいることには意味があると思うのです。
複業は、子どもたちへの贈り物でもある
複業をして得られるのは、先生個人の満足だけではありません。
学校に還り、子ども達にも還っていくはずです。
- 社会との接点がある先生の言葉には、説得力がある
- 教室の外で学び続ける姿は、子どもにとって最高のロールモデルになる
- 先生が自分の人生を楽しんでいることで、子どもも安心して未来を描ける
- 学校の業務効率化のヒントを外界で得ることができる
- 保護者理解が深まる(保護者の90%以上が営利事業者)
簡単にあげるだけでもこれだけの効果が期待できます。
子ども達がより柔軟に生きる先生の姿を見て育てば、10年後の社会はもっと面白くなる。
冒険心のある先生が正しく複業を志すことは、社会開発につながっているという事実を忘れないでください。
最後に|やってみたいを力に
自分が受け持つ生徒に「これやってみたいんだけどうまく行くかわからないんだよね」と相談されたらどう答えるでしょうか。
きっと皆さんならこう言うはずです「やってみたらいいじゃない」。
本記事に辿りついてくださった先生も、何か燻るものがあるはず。
であれば、小さな一歩からでも動いてみましょう。
何か動けば必ずその答えが返ってきます。うまく行くもよし、そうでないのであればその選択肢は違っていたことの確認になります。
複業に関心を持った心に蓋をせず、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
私たち特定非営利活動法人越境先生では、学校の先生の越境・複業を促進していく仲間を募集しています!
私たちの活動に関心を持ち、仲間に出会いたいと考える方はぜひ以下のページもご覧ください。