「講演を頼まれたけど、兼業申請しないといけない?」
「原稿料って受け取っていいの?」
—— そんな疑問を抱く教員の方は、少なくないはずです。
実は、単発の講演や執筆に関する謝金は、多くの場合“副業”にあたらず、兼業申請も不要とされています。
しかし、現場ではそれが十分に共有されておらず、慣習や空気で「出しておいた方が無難」とされるケースも。この記事では、制度上の根拠や各自治体・国の事例をもとに、単発の講演・執筆活動に関する正しい理解と、実務での対応方法を、初めての方にもわかりやすく解説します。
補足:「副業」という言葉について
「副業」という言葉について、本来行政においては、職務を”兼ねる”という「兼業」という表現が正確です。
また、特定非営利活動法人 越境先生では、一人の人が複数の仕事を持ち、それぞれがその人の個性としてつながり合っている働き方を、本業のかたわらで行うサイドジョブとしての副業ではなく「複業」として前向きに捉えています。
ですが、この記事では、兼業・複業よりも、広く一般的でなじみのある表現として「副業」という言葉を使っています。ご理解ください。
関連記事:副業を越えて「複業」へ|教師のマルチキャリアが子どもにもたらす未来
結論:講演・執筆の謝金は「原則として申請不要」です
前述のとおり、単発の講演や執筆に関する謝金は、多くの場合“副業”にあたらず、兼業申請も不要とされています。
根拠1:総務省の公式見解(調査結果および公開資料など)
根拠1-1:令和2年 勤務条件等に関する附帯調査
総務省が作成している「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について(令和2年1月10日総行公第1号)では、
継続的又は定期的ではない単発的な講演等に対する謝礼は、許可が必要な兼業に該当しない
と記載があります。
総務省「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査(勤務条件等に関する附帯調
査)の結果等について・別添2」より引用
根拠1-2:総務省の公開資料および公式回答
かつて、総務省では「地方公務員が受ける単発の講演や執筆等による謝金について「許可を要しない」とする資料が掲載されておりました。
特定非営利団体 越境先生では、総務省に対して、単発の講演や執筆に係る謝金について、2025年7月時点の見解を問い合わせいたしました。
以下、質問と回答です。
質問:かつて貴省(総務省)の以下ページ(https://www.soumu.go.jp/main_content/000664112.pdf)において、地方公務員が受ける単発の講演や執筆等による謝金について「許可を要しない」とする資料が掲載されていたことを記録しております。
しかし、現在では該当ページが非公開となっており、弊法人が調査した範囲では、地方公務員による単発の謝金受領(例:講演・執筆等)に関して「許可を要しない」と明示された資料を、貴省Webサイト上で確認することができておりません。
つきましては、以下2点についてご教示いただけますと幸いです。
1. 単発の講演や執筆等による謝金について、「許可を要しない」とする以前の見解は現在も維持されているのか。
2. 現在その見解が示されていないとすれば、その理由や背景をご教示いただけないか。
回答:令和7年6月11日に「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について(令和7年6月11日総行公第72号)」を発出したため、HPの掲載形式を変更しています。過去の助言通知を含め、以下URLをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/hukumu.html
質問1及び2について
ご質問にあるような講演料や原稿料などの謝金に関する一般的な解釈について、令和7年6月11日発出の助言通知の前後で変更等は生じておりません。
その上で、地方公務員法第38条第1項において、一般職の地方公務員(パートタイムの会計年度任用職員を除く。)は、任命権者の許可を受けなければ、
① 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、もしくは
② 自ら営利企業を営み、又は
③ 報酬を得ていかなる事業もしくは事務に従事してはならない、
とされています。
制限される行為の③でいう「報酬」とは、一般論として、給料、手当などの名称のいかんをとわず、労務、労働の対価として支給あるいは給付されるものをいうものとされています。しかし、収入がすべて報酬であるとされるのではなく、労務、労働の対価ではない給付、たとえば、講演料や原稿料などの謝金や、あるいは実費弁償としての車代は報酬には該当しないものと解されています。
要約すると、以下となります。
- 地方公務員は「報酬を得る事業への従事」を禁止され、営利企業とのかかわりには任命権者の許可が必要(地方公務員法第38条第1項)
- ここでいう「報酬」は、給与や手当のような労務の対価を指し、講演料・原稿料などの一回限りの謝金や交通費などの実費弁償は含まれない
- つまり、単発の講演や執筆で受け取る謝金は「報酬」にあたらず、許可を取る必要はない
以上の理由から、講演・執筆の謝金は「原則として申請不要」と理解できます。
根拠2:国家公務員の基準(現行)
内閣官房の「国家公務員の兼業に関するガイドライン」では、次のように記されています。
単発的な講演や雑誌等への執筆で報酬を得る場合は、継続的・定期的に従事することには当たらない
これは、地方公務員にも類似する基準として参考にできます。
以上の理由から、そもそも単発的な講演や雑誌等への執筆は「副業」にあたらない=申請不要、と理解できます。
ちなみに、そもそも公務員の兼業・副業に申請が必要とされる理由・背景については、以下の記事で紹介しています。参考にしてください。
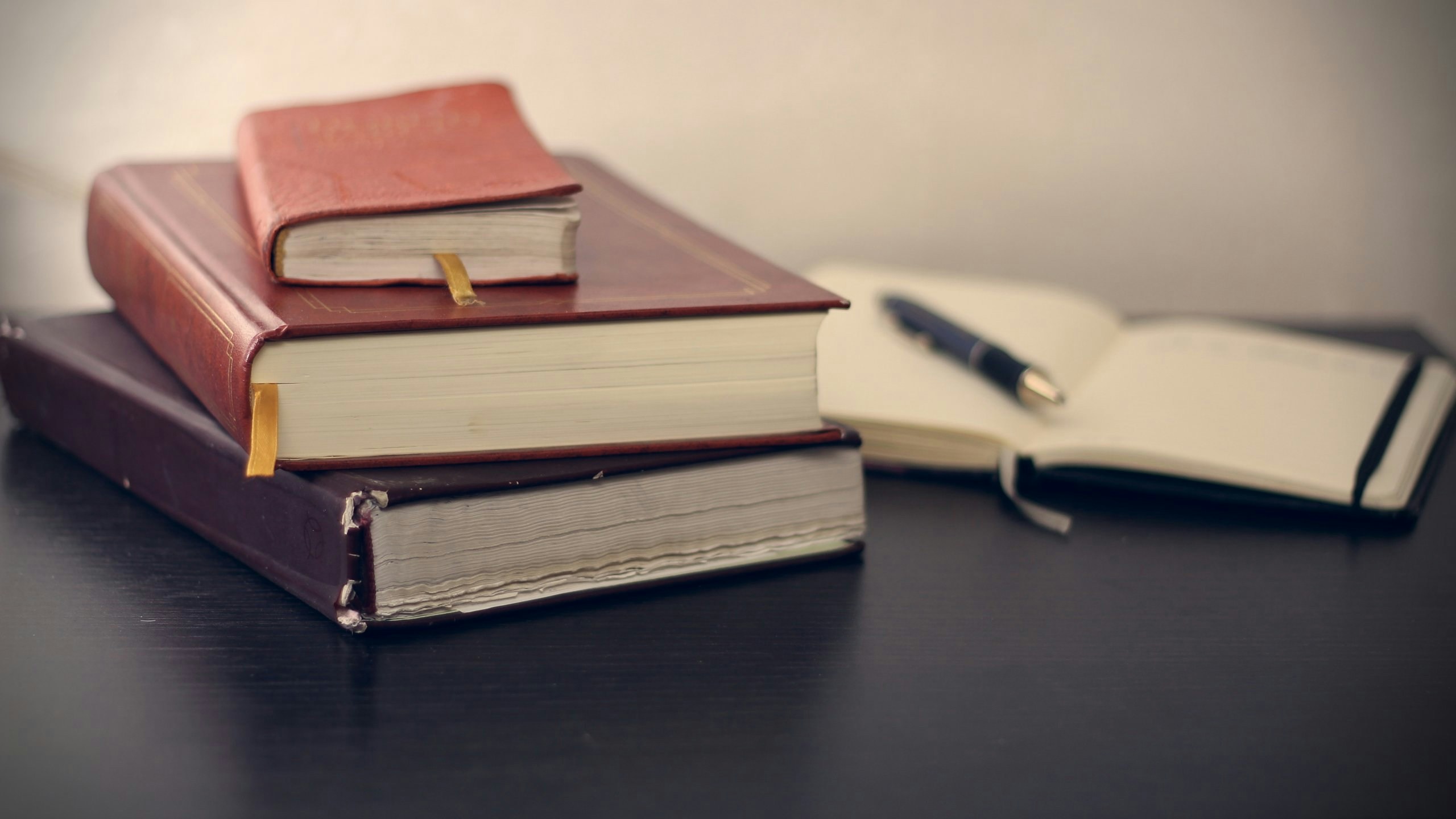
実際に、申請は必要ないのか?
上記の根拠から、本来は兼業申請不要と理解できる単発の講演や原稿執筆。
ですが、実際の現場では、
- 制度と運用の理解が校内で浸透していない
- 過去の慣習で「とりあえず出しておこう」とされている
- 管理職の判断で形式上の申請を求められる
などの理由で、申請を求められる場合もあります。
このような場合、どうするのがよいのでしょうか?
どう対応すればいい?迷ったときの3ステップ
形式的な書類提出が求められる場合でも、それが自己実現の第一歩であるなら、ぜひ誠実に対応しましょう。
ポイントは、以下の通りです。
- 講演・執筆が単発であることを資料等で明記する
- 高額な報酬でないことを添えて説明する
- 必要に応じて、制度根拠(総務省見解・国家ガイドライン)を提示す
(こちらの記事)でも触れている通り、教員の副業が原則禁止になっている大きな要因の一つが「職務専念義務の担保」です。
要は、副業のせいで本業がおろそかになってはならない、ということ。
そのため、今皆さんが検討している講演や原稿執筆が、この「職務専念義務の担保」規定に抵触しないことを、正しくわかりやすく伝えることが大切です。
逆に、そもそも継続的な関わりである場合や、高額な報酬が発生する場合など、上記のポイントに抵触するのであれば、兼業申請をした上で取り組む必要があるかもしれません。
参考事例:自治体の実務運用(例:生駒市)
自治体によっては、ガイドラインを定め「兼業申請」と「口頭確認」を併用している地域もあります。
例えば、公益財団法人 東京市町村自治調査会の「公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書」では、2015年 2 月に「生駒市人材育成基本方針」を策定し、「副業制度」を導入している生駒市の取り組みが紹介されています。
公益財団法人 東京市町村自治調査会「公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書」より引用
副業制度の利用実績について
制度利用については、当初想定していたのはNPOの活動に週 1 くらいのペースで参画するようなものであったが、実績としては年に数回の単発な取組が多い。
執筆活動と講師は「謝礼」の側面が強いため、単発の講演依頼や執筆活動は報酬額を確認の上、口頭でOKとしており、今回の副業制度の枠外ということで許可申請は求めていない。
出典:公益財団法人 東京市町村自治調査会『公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書』(p.35)
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/900/fukugyo_all.pdf
余談ですが、同報告書によると、生駒市では「当初在職 3 年以上を申請要件としていたが、 1 年間やってみて本業に支障が特になかったので、在職 1 年以上にハードルを下げた」など、実情に合わせた改善と制度運用が進んでいます。
現場の管理職や担当者への説明の際に、参考になれば幸いです。

越境先生として伝えたいこと
私たち越境先生は、教員の講演や執筆活動を「副収入の手段」ではなく、
「外の世界とつながる入り口」
と捉えています。
本来、こうした活動を通して得た学びや刺激こそが、学校に還元され、教育の幅を広げる財産になります。
不必要に萎縮せず、制度を理解したうえで、誠実かつ積極的に取り組んでいきましょう。

「副業できる教師」を増やしたい——そのために
特定非営利活動法人 越境先生では、副業や兼業だけでなく、広く「越境」によって生まれた好事例を一つでも多く可視化し、仕組みとして後押しすることをミッションとして活動しています。
「学校の外の経験が、教育に還元される」
そんな当たり前を、現場でも社会でも広げていくために、私たちは活動を続けています。
この取り組みに共感いただけたら…
越境先生では、こうした取り組みを支えてくださる寄付パートナーを募集しています。
月1,000円から、教育の未来を変えるチャレンジに参加いただけます。
先生が変われば、学校が変わる。学校が変われば、社会が変わる。
一緒に社会を変えてみませんか?
書籍紹介
本記事のような兼業・複業にまつわる、現職・元教員のリアルな実践、制度のポイント、心構えまで丁寧にまとめた一冊です。
よくある質問(FAQ)
Q. 教員が講演で謝金をもらったら副業ですか?
→ いいえ。単発かつ非継続的であれば、副業には該当しません。
Q. 原稿料はどうですか?
→ 一度限りの執筆活動なら申請不要です。連載など継続的なら個別判断が必要です。
Q. 「迷ったら出しておいて」と言われましたが?
→ 誠実に対応しつつ、制度上不要なことを丁寧に説明することで、信頼関係が築けます。
Q. 副業と兼業、複業はどうちがいますか?
→越境先生では、以下の通り整理しています。
副業:本業のかたわらで行う仕事。あくまで“主”の仕事があっての“サイドジョブ”。
兼業:行政でよく使われる言葉で、職務を“兼ねる”という形式的な意味合いが強い。
複業:一人の人が複数の仕事を持ち、それぞれがその人の個性としてつながり合っている働き方。


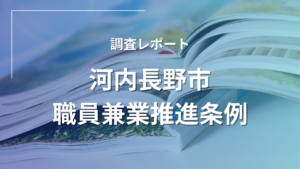



コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 特定非営利活動法人 越境先生 教員の講演や執筆は副業になる?兼業申請は必要?制度と実態を徹底解説 … […]