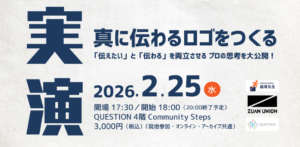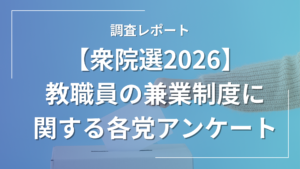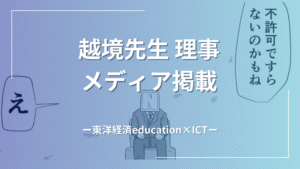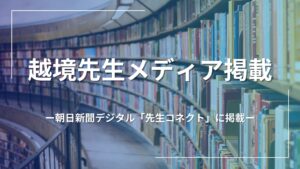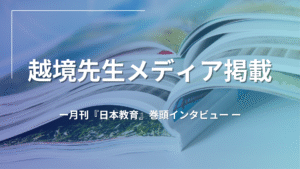このたび、教員の越境・複業を推進することを目的に、特定非営利活動法人「越境先生」(代表理事:前田 央昭、以下「越境先生」)が2025年1月末に正式に法人登記を完了しました。 越境先生は、神戸市教職員組合と連携し、部活動の地域移行事業「KOBE◆KATSU(コベカツ)」にかかる教職員参画制度について、神戸市教育委員会との協議の場に参加するほか、阪神地区で教育に関心のある市議会議員向けの勉強会にて講師を務めるなど、各自治体関係者との連携を強化しています。 これらの取り組みを通じて、教師の越境や複業の可能性を広げ、教育現場の活性化を目指すプロジェクトを本格的にスタートいたします。
■ 越境先生設立の背景:社会との接続を法律により制限されている教員たち
全国の公立学校教員は、地方公務員法第38条および教育公務員特例法第17条の各自治体での解釈により、複業へのチャレンジに厳しい制限が課されています。
特に教育公務員特例法第17条は、教育に資する活動や修養を柔軟に認める趣旨で定められたものですが、一部の条文解釈が独り歩きし、一般公務員よりも厳しい運用が行われている現状があります。その結果、教員の成長や挑戦の機会が限られ、教育の多様性や革新が妨げられていることが問題視されています。

越境先生は、こうした課題を社会に広く知ってもらい、法制度の再検討を含めた議論を促進することで、教育現場と社会をつなぐ新たな仕組みづくりを目指します。
■ 団体のビジョン:先生の「やりたい」を守る
「子どもたち1人ひとりに可能性があるように、1人ひとりの先生にも可能性がある」
という思いのもと、先生が自身の可能性を最大限に発揮できる環境づくりを目指しています。
教員の越境・複業を推進し、先生たちが主体的に学び、挑戦する姿を子どもたちに見せることで、未来の教育をより豊かにすることを目指します。
団体のビジョン:https://ekkyosensei.jp/about-us/
■ 自治体との連携状況
アドバイザーとして、神戸市:「KOBE◆KATSU」の協議の場に参画
「KOBE◆KATSU」支援のため、神戸市教育委員会・神戸市教職員組合の協議の場にアドバイザーとして参画しました。
支援の背景
神戸市では、少子化や教員不足の影響で、中学校の部活動が相次いで廃部・休部となる事態が深刻化しており、その対策として、2026年度から「KOBE◆KATSU」(以下、コベカツ)という部活動の地域移行施策が導入される予定です。
無償でも申請が必須。教員だけが抱える“不合理な申請手続き”
コベカツは、一般行政職員が無償で参加する場合は申請不要です。しかし、これまで部活動を担ってきた教員が、コベカツで生徒を継続してサポートする場合、兼業に関する規定上、有償・無償を問わず「兼業申請」が必要となることがわかりました。
これにより「同じ公務員でも教職員だけが許可を得ないと活動できない」という不合理な状況が生じる上、教員・自治体それぞれに新たな事務負担が発生します。
教員が申請手続きの煩雑さや法律上のリスクを理由にコベカツへの参加を断念すれば、例えば民間のクラブだけでは運営が行き届きにくい都市部から離れた地域などで、子どもたちの受け入れ先が確保できなくなることが懸念されます。
実際に、文部科学省が行った「地方公共団体の部活動改革取組状況について フォローアップ調査(2024年)」では、「指導者の量の確保」が地域クラブ活動の最も上位の課題であるという結果になっています。
◆参考◆ 地域クラブ活動の課題 上位4つ
部活動の地域連携・地域移行が進むなか、調査では地域クラブ活動の課題も見えてきました。自治体が地域クラブ活動の課題として認識している事項では、以下4つの回答が多く挙げられました。

こうした問題は、決して神戸市だけの課題ではありません。地域クラブへの参画を希望する教職員の兼業の在り方が未整備なまま全国で地域展開が進めば、各地で同様の混乱が予想されます。
越境先生では、これらの課題を解決するため、教育関連法を専門とする弁護士や大学研究室などと連携し、神戸市教育委員会・神戸市教職員組合の協議の場にアドバイザーとして参画しました。今後も解決に向けてサポートを続けていく予定です。
阪神地区:市議会議員向け勉強会を実施
宝塚市の中山ゆうすけ議員主催による、教育に関心のある市議会議員の方々を招いた勉強会に講師として登壇しました。
教員の越境のし辛さとそれを原因とする学校教育の課題について講演し、今後の市政においてどのような解決方法を取るべきか協議しました。
***
この他、越境先生では、教員の越境学習(学校の枠を越え、学校とは異なる環境で体験する学び)の促進のため、カリキュラムの開発や提案、連携可能性を模索しています。
さらに、各都市の教育委員会に対し、教員の越境のし辛さに関する課題のヒアリングを行い、それぞれの課題感に即したプログラム開発を進めるなど、学校が外部連携を行う際、持続的に民間企業含む外部団体と連携していくためのノウハウ等を提供する予定です。
■ 今後の活動計画
私たちは、「境界を、越えろ」というメッセージを掲げ、教師が本来持つ可能性を解放し、社会全体に影響を与えるための活動を展開します。
- 透明性のあるガイドラインの策定
地方公務員法第38条や教育公務員特例法第17条の解釈が自治体によって異なる現状を是正すべく、透明性のあるガイドラインの策定、および適正な制度運用を提言します。
まず初めに、教員の兼業に関する基準や自治体ごとの運用実態を調査。適宜全国教育委員会へ開示請求を行い、回答内容を公表するとともに、実施結果を分析・考察し、教員の越境・複業を促進するための制度設計や政策提言に活用します。
- 教員の越境学習プログラム開発と、専門家連携によるエビデンスの確立
教員が学校の枠を超え、企業やNPOなど社会の第一線で学ぶ「越境学習プログラム」を開発し、教育現場で活かせるスキルや知見の習得を支援します。
また、越境先生の活動を通じて得た知見を学術研究に活かし、教員の越境や複業が教育に与える影響を専門家とともに分析。実証データに基づく研究を進め、教育の質向上に寄与するエビデンスの確立を目指します。
自治体との協働では、研究成果を制度設計や政策提言につなげ、持続可能な教育改革を推進します。
- 全国の先生と、教員の越境・複業に関するコミュニティを形成
教員同士が学び合い、実践知を共有できるコミュニティを全国規模で形成します。
複業や越境の経験を持つ教員や、これから挑戦したいと考える教員がつながり、知見を交換できる場を提供。オンライン・オフラインでの学習会や交流イベントを開催し、実践者の声を生かした学びの機会を創出します。
これにより、教員の越境・複業の知見を深化させ、実践例を蓄積します。
教員が社会と接続し、多様な経験を活かせる「越境・複業先進都市」の創造
上記の活動を通して、私たちが目指すのは、教員が、複業や外部活動を円滑に行える「先行自治体でのモデルケース(越境・複業先進都市)」の創造と、その成果の全国への波及です。
教員が可能性を制限されず、社会との接続点を広げることで、教育現場はより創造的で開かれたものになります。私たちはその挑戦を後押しし、越境する先生たちを起点に、教育と社会の未来を共に創っていきます。
■ 代表理事のコメント
「越境先生を設立したのは、“先生のやりたい”が学校の枠に阻まれる現状を変えたいからです。
先生だって、一人の社会人として成長し、挑戦できるはず。
でも今は、法制度や慣習がそれを難しくしている。教員の越境や複業は、一部の特別な人だけのものではなく、より良い教育をつくるための選択肢であるべきです。
私自身、教員として働きながら”外の世界”に飛び出し、その経験が教育に還元できる手応えを感じました。そんな経験を、もっと多くの先生に届けたい。
そして、越境する先生たちが生まれることで、教育がもっと面白く、社会とつながるものになっていくはず。
そのために、自治体や専門家、企業と協力し、制度を整え、学びの機会を広げ、エビデンスを積み上げていきます。
一緒に、教育と社会の境界を越え、新しい未来をつくっていきましょう。」
(代表理事:前田央昭)
■ ご支援のお願い:月額パートナー募集
越境先生では、教員の越境・複業に共感いただける個人・企業の皆さまからのご支援を募っています。
毎月定額でご支援いただくことで、講演・ワークショップの開催や自治体との連携推進など、教育現場を取り巻く課題解決に向けた活動を強化していきます。
特設ページ:https://ekkyosensei.jp/lp/partner/
「主体的に挑戦する輪が広がり、越境する教師たちを起点に、社会はもっともっと面白くなっていく。」
―― この未来を共に目指していただける皆さまのご支援を、心よりお待ちしております。



■ 本件に関するお問い合わせ
特定非営利活動法人 越境先生
E-mail:info@ekkyosensei.jp
HP:https://ekkyosensei.jp/
※プレス関係者の方からの取材やコラボレーションに関するご相談は、上記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。